歯周病になりやすい人にはどんな特徴がある?予防法も
こんにちは。東京都港区「虎ノ門ヒルズ駅」より徒歩1分にある歯医者「虎ノ門ヒルズ駅前歯科」です。
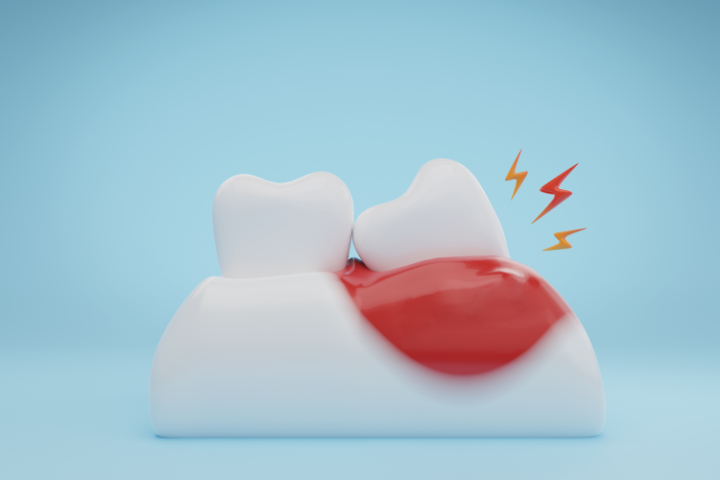
「歯茎から血が出る」「口の中がネバつく」「歯がグラグラしてきた」という症状に心当たりがある場合、歯周病のサインかもしれません。歯周病は、成人の8割以上がかかるともいわれている国民病であり、進行すると歯を失う原因にもなります。
しかし、毎日のケアと少しの意識で予防できる病気でもあります。
この記事では、歯周病になりやすい人の特徴や具体的な予防法、また、歯周病の原因についてもわかりやすく解説します。
歯周病になる原因

歯周病は、歯を支える組織(歯肉や骨)が細菌によって破壊されていく病気です。初期段階では歯肉炎と呼ばれ、歯茎の腫れや出血が見られます。進行すると歯周炎となり、歯槽骨が溶け、最終的には歯が抜け落ちてしまうこともあります。
歯周病の原因は主に細菌の感染ですが、それを引き起こす背景には複数の要因が複雑に絡み合っています。
プラークの蓄積
歯の表面に付着する白っぽいネバついた汚れが、プラークと呼ばれる細菌の集合体です。このプラークが、歯周病の最も大きな原因になります。
特に、歯と歯茎の境目は汚れがたまりやすく、そこに潜む細菌が時間をかけて繁殖することで、歯茎に炎症が起こりやすくなるのです。さらに、放置すればプラークは歯石へと変化し、より強固に歯に付着するため、セルフケアだけでは取り除けなくなります。
歯石の放置
歯の表面にたまったプラークが唾液に反応して硬くなると、歯石と呼ばれるかたい沈着物に変化します。歯石はザラつきがあり、細菌がさらに付着しやすい環境を作り出します。
そのまま放置すると、歯茎への刺激や炎症が強まり、歯周病が悪化する原因となります。一度固まった歯石は歯ブラシでは取り除けず、歯科医院での専門的なクリーニングが必要不可欠です。
生活習慣
砂糖を多く含むお菓子や飲み物を長時間にわたって頻繁に口にしていると、口腔内が酸性に傾き、歯周病菌が活発に働きやすい状態になります。また、慢性的な夜更かしや睡眠不足が続くと、免疫力が低下し、唾液の分泌量が減って口の中の自浄作用が弱まります。
このような生活習慣によって、口内に菌が増殖しやすくなり、歯茎に炎症が起こるリスクが高まります。
歯並びの乱れ
歯並びが乱れていると、歯と歯の間に汚れがたまりやすく、ブラッシングでも磨き残しが出やすくなります。特に、重なり合った歯や奥歯の隙間は、プラークが蓄積しやすく、歯周病菌の温床となります。
さらに、噛み合わせのバランスが崩れることで、一部の歯や歯茎に過剰な負担がかかり、炎症や歯の動揺を引き起こす可能性もあります。歯列矯正や定期的な歯科ケアを通じて、口内を清潔に保つことが大切です。
歯ぎしり・食いしばりの癖
歯ぎしりや食いしばりの癖は、歯周病の直接的な原因ではないものの、歯茎や歯を支える骨に過剰な力を加えます。歯周組織にダメージを与え、炎症を悪化させる要因になります。
特に、すでに歯周病が進行している場合、歯の揺れや歯茎の後退を加速させるリスクがあります。就寝中など無意識に起こることが多いため、自覚がなくても症状が進んでいる可能性があります。予防には、歯科医による診断やマウスピースによる保護が有効です。
歯周病になりやすい人にはどんな特徴がある?

歯周病には、体質や年齢などさまざまな要因が関係しています。特に、口内環境が生活習慣に影響を受けている場合もあり、食生活や癖によって歯周病を引き起こしている可能性があります。
歯磨きが不十分な人
歯周病になりやすい人の特徴のひとつに、日々の歯磨きが適切に行われていないことが挙げられます。磨き残しがあると、歯垢や食べかすが歯茎周辺にたまりやすくなり、そこから細菌が増殖して炎症を引き起こす原因になります。
特に、歯と歯茎の境目や奥歯の裏側は汚れが残りやすく、気づかぬうちに歯周病が進行することもあります。歯ブラシの使い方や補助的な清掃用具を見直し、丁寧なケアを心がけることが大切です。
歯並びが乱れている人
歯並びが乱れていると、歯と歯が重なったり狭い隙間ができたりして、汚れやプラークがたまりやすくなります。そのため、虫歯や歯周病の発症リスクが高くなる傾向があります。
通常の歯ブラシだけでは届きにくい部位が多いため、フロスや歯間ブラシといった補助的な清掃用具を併用し、歯と歯茎の境目まで丁寧にケアすることが不可欠です。歯並びが気になる場合は、歯科医に相談し、適切な予防策をとることも検討しましょう。
喫煙習慣がある人
喫煙習慣のある人は、歯周病のリスクが高いとされています。タバコに含まれるニコチンや有害物質は血管を収縮させ、歯茎への血流を妨げるため、組織の修復力や免疫反応が低下します。その結果、歯周病菌に対する抵抗力が弱まり、炎症が起きやすく、進行もしやすくなります。
さらに、症状に気づきにくくなるため発見が遅れたり、治療の効果も出にくくなったりします。歯茎の健康を守るには、禁煙することも大切です。
口呼吸の人
口呼吸が習慣化している人は、常に口の中が乾燥しやすく、歯周病を含むさまざまな口腔トラブルを引き起こしやすくなります。口腔内が乾いていると、唾液による自浄作用や抗菌作用が十分に働かず、細菌の繁殖が加速してしまいます。
とくに、無意識に口を開けているポカン口の状態が続くと、歯茎の炎症を助長する恐れがあります。呼吸法の見直しや、口周りの筋肉を鍛えるトレーニングを取り入れることで、改善が期待できます。
歯周病を予防する方法

歯周病を予防するためには、正しい口腔ケアの方法を身に付けることや生活習慣を整えることが重要です。特に、自宅での口腔ケアだけでは歯周病の原因となる細菌や汚れが除去しきれない場合も多いため、定期的に歯科検診やクリーニングを受けることが歯周病予防につながります。
正しくブラッシングを行う
歯周病を予防するためには、正しいブラッシングが重要です。歯と歯茎の境目に歯ブラシを当てて小刻みにブラッシングを行うことが効果的です。また、自分の歯に合う歯ブラシを使用することや食事後にこまめに歯磨きを行うことで、口内の清潔を保てます。
デンタルフロスや歯間ブラシを活用する
歯ブラシのみでは取り切れない汚れや歯と歯の間に蓄積しているプラークは、デンタルフロスや歯間ブラシを使用して除去しましょう。こまめなケアを行うことで、歯周病のリスクを大幅に下げられます。
バランスの良い食事をする
歯周病を予防するには、日々の食事内容にも目を向けることが大切です。ビタミンCやカルシウム、良質なタンパク質などの栄養素は、歯茎や骨の健康を維持し、炎症への抵抗力を高めてくれます。
また、食事の際によく噛むことによって唾液の分泌が促進され、口内の細菌や汚れを自然に洗い流す効果も期待できます。バランスの取れた食生活は、体の健康だけでなく、お口の中の環境を整えるうえでも欠かせません。
定期的に歯科検診を受ける
口内の状態に合わせて3ヶ月~6ヶ月に1回の頻度で、歯科検診を受けましょう。定期的に歯科検診を受けることで、自宅でのケアのみでは落としきれない汚れを除去してもらえます。
また、自分では気づきにくい歯周病を発見し、早期に治療を始めることが可能になります。
まとめ

歯周病は、歯を支える組織が細菌の影響で壊れていく病気です。初期の歯肉炎から進行すると歯周炎となり、最悪の場合歯を失うこともあります。
主な原因はプラークや歯石の蓄積、歯磨き不足、喫煙、口呼吸、歯並びの乱れ、歯ぎしりなど多岐にわたります。予防には正しいブラッシングや補助清掃用具の使用、バランスの取れた食事、定期的な歯科検診が欠かせません。
日々の習慣を見直すことが歯茎の健康維持につながります。
歯周病にお悩みの方は、東京都港区「虎ノ門ヒルズ駅」より徒歩1分にある歯医者「虎ノ門ヒルズ駅前歯科」にお気軽にご相談ください。
当院は、妥協なき歯科医療を目指して幅広い治療に対応しています。虫歯・歯周病治療や精密根管治療、生体親和性、インプラント、矯正治療など、さまざまな診療を行っています。


